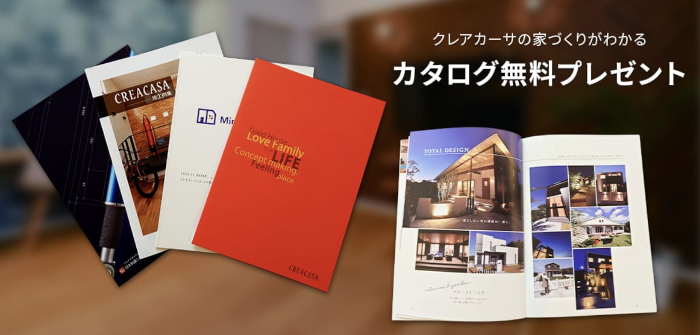自宅で民泊をするなら|必要な手続き・運営スタイル・始め方を徹底解説!

使っていない自宅の一部を有効活用して、収益を得られるのが民泊です。
自宅で民泊を始めるなら、法律や運営スタイルなど、押さえるべきポイントは多いものの、手順を理解すればスムーズに進められます。
また、安定した収入源が見込めるため、副業として民泊を始める方が多いのも特徴です。
そこで本記事では、民泊を始めるための手順や注意点をわかりやすくまとめましたので、参考にしてください。
● 民泊を始める前に必要な事前準備についてわかりやすく解説いたします。
● 民泊に必要な手続きやメリット・デメリットについても紹介します。
● クレアカーサは、茨城県で民泊を想定した家づくりの提案も行っています。
目次
自宅で民泊を始める前に!3つの確認すべきこと

自宅で民泊を始めるには、利用する物件が賃貸もしくは自己所有かによって必要な手続きが異なります。
ここでは、物件の種類ごとの特徴と注意点を解説します。
賃貸物件の場合
賃貸物件の場合は、賃貸借契約書を確認し民泊が認められているか確認が必要です。
認められている場合、オーナーや管理会社の承諾を得て自治体へ届け出を行います。
認められていない場合は、そもそも運営はできません。
無断で民泊を始めた場合は、賃貸借契約違反となり契約解除される可能性があります。
参照:民法第六百十二条
自己所有・戸建ての場合
民泊を自己所有の戸建て行う場合、比較的自由に運営できる始め方です。
比較的自由に運営できますが、自治体によって条例で制限されているケースがあるので、必ず事前に確認してください。
民泊の運営を行っていい自治体なら、担当者と相談しながら必要な手続きを進めます。
自己所有・マンションの場合
マンションやアパートなど集合住宅の一室を民泊として運営する場合、自己所有物件であったとしても管理規約の確認が必要です。
規約で許可されている場合、民泊を運営して問題ないといえます。
ところが、管理組合のあるマンションやアパートの場合は規約で民泊が許可されていたとしても、管理組合の承認が得られなければ運営できません。
さらに、利用マナーや騒音トラブルを防ぐため、ルール作りを徹底する必要があります。
事前に管理組合や住民と、良好なコミュニケーションを築くことが円滑な民泊運営につながるといえます。
民泊を自宅で始める際の運営スタイル

民泊を自宅で始める際の運営スタイルは、「ホームステイ(家主居住)型」と「家主不在型」の2種類です。
運営スタイルによって届出や申請方法が異なります。
それぞれの特徴を解説します。
ホームステイ(家主居住)型
ホームステイ(家主居住)型は、自宅に住みながら部屋の一部を貸し出すスタイルで、旅行者との交流を楽しみたい方におすすめです。
家主が常駐するため、宿泊者の管理がしやすく、トラブルも未然に防ぎやすいメリットがあります。
住宅宿泊事業法に基づいた届出を行うと180日以内の営業が許可されます。
参照:住宅宿泊事業法
家主不在型
相続した自宅をリノベーションして民泊を運営する、別荘や投資用のマンションを活用するなど、住宅全体を貸し出すスタイルが、家主不在型の民泊です。
空き家や別荘を有効活用でき、より多くの宿泊者を受け入れられるメリットがあります。
家主不在型は入居者の管理が難しくなるため、騒音やゴミ出しなどのトラブルを未然に防ぐ工夫が必要です。
ホームステイ型民泊との主な違いは、消防法に定められたホテルや旅館並みの消防設備の義務化が挙げられます。
自宅で民泊の始め方|7つのステップ

自宅で民泊を始める際に、法的な手続きや届出、設備の要件を揃えるなど計画的な準備が必要です。
トラブルの原因を避け、スムーズに運営を開始するための7つのステップを紹介します。
①自治体や関係機関へ相談する
民泊を始める前に、関係機関へ以下のような届出や相談が必要です。
| 主な届出の種類 | 確認する内容 |
| 住宅宿泊事業法か旅館業法 | ホームステイ(家主居住)型か家主不在型、どちらにするか決める |
| 消防法 | 消火器や火災警報器の設置、非常口の確保 |
| 建築基準法 | 「住宅」から「宿泊施設」に用途変更が必要か |
| 税金に関する法律 | 所得税や住民税、固定資産税や事業税について税務署や専門家に相談 |
民泊のルールは、自治体によって異なります。
なにから始めればよいかわからない場合は、国土交通省の民泊制度コールセンターや、各自治体の窓口から相談可能です。
②設備の要件を揃える
民泊の運営には、住宅宿泊事業法で以下の設備の設置が義務付けられています。
● 台所…調理ができる環境
● 浴室…シャワーや浴槽がある
● 便所…トイレ機能
● 洗面設備…洗面台や水道設備
また、「生活するうえで最低限必要な設備が整っていること」も民泊の始め方として大切な条件です。
必要に応じて換気設備や給湯設備、収納スペースなどの設置や清潔な寝具の用意など自治体ごとのルール確認も同時に進めます。
参照:住宅宿泊事業法
③リノベーション・清掃
快適な空間を提供するため、必要に応じてリノベーションの実施をおすすめします。
壁紙の張り替えや家具の配置を工夫するだけでも、印象が大きく変わります。
また、宿泊者の印象を大きく左右するのは清潔さといっても過言ではありません。
清潔な民泊は、高評価なレビューが書き込まれる可能性があり新規の顧客やリピーターの獲得につながるといえます。
清掃の手間を減らし高品質な空間を保つため、清掃業者の利用もおすすめです。
④開業に必要な許可・届出を行う
民泊の営業を始めるにあたって、開業に必要な許可・届出を行う必要があります。
自治体によってルールが異なる場合がありますが、主に以下のような内容です。
● 住宅宿泊事業法または旅館業法よる許可申請
● 建築基準法
● 消防法
● 賃貸物件の場合、オーナーや管理組合の許可
書類に不備があると民泊営業の許可が下りないため、ひとつひとつ確認しながら慎重に進めることが大切です。
参照:厚生労働省「民泊サービスを始める皆様へ-簡易宿所営業の許可取得の手引き-」、総務省消防庁「防火対策の推進等」
⑤必要な家具・寝具・アメニティなどを用意
宿泊者が快適に過ごせるよう、家具や寝具、アメニティなど用意します。
シャンプーやせっけん、歯ブラシなどの消耗品はもちろん、寝具やタオルなど肌に直接触れるものは清潔さも重要です。
また、電子レンジや炊飯器、鍋や食器などキッチン用品を揃えると長期滞在のゲストにも喜ばれます。
⑥旅行者用の予約サイトに登録
集客には、民泊を専門に扱う予約サイトへの登録を行います。
主な民泊予約サイトと特徴を以下にまとめました。
| サイト名 | 特徴 | URL |
| Airbnb(エアビー) |
集客力が高く、個人でも簡単に民泊を始められる民泊専用サイト 集客力の高さが特徴 |
https://www.airbnb.jp/ |
| Booking.com(ブッキング・ドットコム) |
世界中の旅行者にアプローチできる。 柔軟な料金設定や予約管理が可能。 |
https://partner.booking.com/ja |
| ステイジャパン | 日本国内に特化している民泊専用サイト | https://stayjapan.com/ |
集客力アップにつなげるため、民泊の魅力を写真や文章を工夫し掲載することをおすすめします。
⑦必要に応じて開業届を提出
民泊の収益が副業の場合は年間所得20万円、本業の場合は年間48万円以上になると開業届が必要です。
開業届を提出することで、事業として認められます。
さらに確定申告によって経費の幅が広がり、税負担を軽減できます。
自宅で民泊の始め方|必要な手続き

民泊を自宅で始める際、法律で定められた手続きを済ませる必要があります。
確認や許可、届出を怠ると、罰則の対象になることもあるので、注意が必要です。
必要な手続きについて以下で詳しく解説します。
消防法令適合通知書を入手する
民泊の開業までに「消防法令適合通知書」の入手が推奨されています。
消防法令適合通知書の提出は必須要項ではありませんが、宿泊者の安全確保のため消火器や火災報知器の設置、避難経路の確保など消防法に基づき整える必要があります。
消防法令に基づく消火設備の適合状況は都道府県ごとに異なりますので、事前に自治体へ確認してください。
不備があると行政指導や行政処分の対象となる可能性があるため、「消防署から安全を認められた」ともいえる消防法令適合通知書の入手をおすすめします。
参照:消防法
住宅宿泊事業届出の必要書類を用意する
民泊を自宅で運営するには、住宅宿泊事業届出に必要事項を記入し、添付書類とあわせて提出する必要があります。
添付書類は、住宅の登記事項証明書や住宅の図面など、定められた12の書類が必要です。
書類に不備があると手続きに遅れが生じるため、事前に自治体のホームページで必要書類の確認をおすすめします。
参照:住宅宿泊事業法
届出番号を見やすい場所に提示する
住宅宿泊事業の届出が受理されると、届出番号が発行されます。
届出番号は、宿泊者が確認できる場所に提示する義務があるので、玄関や受付スペースなど目立つ位置の設置がおすすめです。
民泊予約サイトに登録する際も、届出番号の入力が必要なケースがあります。
届出番号の提示がないと無許可営業と誤解される可能性が高くなるうえ、違反すると行政指導や営業停止の対象になるため、必ず掲示してください。
参照:住宅宿泊事業法
2か月ごとの定期報告も忘れずに
住宅宿泊事業法では、2か月ごとの定期報告が義務付けられています。
義務付けられている報告内容は以下の項目です。
●宿泊者の数
●宿泊日数
●近隣住民からの苦情の有無
●住宅宿泊管理業者への委託の有無
●その他、自治体ごとに必要とされる情報
自治体によって項目が異なる可能性もありますので、事前の確認が必要です。
定期報告を怠ると、業務停止や届出抹消だけでなく、罰金・懲役が科される可能性もあります。
参照:住宅宿泊事業法
自宅で民泊を始めるメリット

自宅で民泊を始めると、初期費用を抑えつつ収益を得られます。
また、不動産の資産価値向上や、副業としての柔軟な運営も魅力です。
それぞれのメリットを詳しく解説します。
初期費用を抑えられる
自宅を民泊に活用すれば、新たに物件を購入する必要がないため初期費用を抑えられます。
資金の用途が設備の準備や申請手続きに限られるため、少ない資金で開業できる点も大きなメリットです。
また、家賃負担がない分、利益を確保しやすい傾向があります。
資産価値が上がる可能性がある
自宅で民泊を始めると、資産価値が上がる可能性があります。
資産価値を高くするため、内装や設備、配管などの改修やこまめなメンテナンスがおすすめです。
たとえ築年数が古い物件でも、メンテナンスが行き届いている民泊は競合と差別化できるため顧客獲得に期待できます。
また、メンテナンスが行き届いている物件なら、不動産市場の価値も高くなる傾向があるため、コストがかかりますが長期的にみると大きなメリットです。
高い収益性が見込める
民泊の宿泊料金は、オーナーが自由に設定できるため高い利益性が見込めます。
市場の需要や観光シーズンに合わせて、自由に調整可能な点が民泊運営のメリットです。
ただし、自治体によって宿泊費用の上限や最低価格が設定されている場合もあります。
相場より極端に高額にすると、消費者保護の観点から問題視されるケースがあるため、自治体のルールやモラルを守った料金設定が大切です。
副業として取り組みやすい
自宅で民泊を始める場合、本業と両立しながら運営できるのも大きなメリットです。
管理業務を代行業者に委託すると、負担を軽減しながら収益を得られます。
また、予約サイトを活用すれば、手間をかけずに宿泊者を集められるため、初心者でも始めやすいビジネスモデルといえます。
自宅で民泊を始める際のデメリット・注意点

民泊には多くのメリットがありますが、事前にデメリットや注意点を確認する必要があります。
適切な対策を講じると、トラブルを回避しながらスムーズな運営が可能です。
民泊の始め方のヒントとして、参考にしてください。
民泊以外の使い方ができない
自宅での民泊は、自由な使い方が制限される点がデメリットです。
自宅の一部または全体を宿泊施設として運用するため、一時的なオフィス利用や、賃貸住宅として貸し出すことが難しくなる場合があります。
民泊以外の用途に変更する可能性がある場合は、自治体のルールや契約内容など事前の確認がおすすめです。
年間の宿泊日数が制限されている
住宅宿泊事業法に基づく民泊は、年間180日以内の営業制限があります。
年間180日と決められた日数内で安定した収益を得るには運営計画を立て、収益シミュレーションを行うことが重要です。
また、旅館業法の「簡易宿所営業」の許可を取得すると180日制限は適用されません。
その場合、避難経路の確保やフロントの設置など、旅館としての施設基準を設ける必要があります。
近隣住民や宿泊者とトラブル発生の可能性がある
民泊は不特定多数の宿泊者を受け入れるため、騒音やゴミ出しなどが原因で近隣住民とトラブルになる可能性があります。
また、室内を土足で歩いてしまう、ゴミの分別を勘違いしてしまうなど文化や習慣の違いで悪意のないトラブル発生の可能性も考慮しなければいけません。
トラブルを未然に防ぐため、宿泊者に向けたルールの徹底・周知や、近隣住民と良好なコミュニケーションなど、普段からの心がけが大切です。
破損や盗難のリスクがある
自宅を民泊にするデメリット・注意点として、宿泊者による家具や設備の破損、盗難のリスクがあります。
万が一に備えたルールの明確化、破損や盗難時の補償制度など事前の準備が大切です。
Airbnbなどの補償制度がある民泊プラットフォームの利用や、民泊保険の加入などリスクの備えが安心感につながります。
管理の手間がかかる
自宅で民泊を始める場合、予約管理や清掃、宿泊者対応など、運営に手間がかかるのがデメリットです。
チェックイン・チェックアウト時や、急なトラブル対応などすべて自分で行うと、負担が大きくなります。
負担軽減のため、以下のような管理方法も有効です。
● 清掃代行サービスを利用し、清掃作業の負担を減らす
● スマートロックを導入し、対面で鍵を渡さなくてもチェックインを可能にする
● 管理会社に運営を委託し、予約管理やゲスト対応を任せる
仕組みを整えると、負担を軽減しながら安定した収益に期待できます。
民泊を禁止している地域がある
自宅で民泊を始める際の注意点として、自治体によっては、条例で民泊を禁止または制限している地域があります。
これらの制限は、住宅宿泊事業法や都市計画法に基づいて自治体が決めたルールです。
民泊を制限している地域の一例として、東京都大田区と京都市の一部地域があります。
東京都大田区では「住居専用地域」の民泊が禁止されており、京都市の一部地域で平日の営業が制限されています。
また、学校周辺や閑静な住宅街では、住民の生活環境を守るために民泊の営業が禁止されているケースもあるため、自治体のルールを確認することが重要です。
住宅ローン控除を受けられない可能性がある
自宅を民泊として運用するデメリットとして、住宅ローン控除の適用外になる可能性があります。
住宅ローン控除は、「自ら居住する住宅」に適用される制度です。
民泊運営が「事業」とみなされると、控除を受けられなくなるケースがあります。
事前に金融機関や税理士に相談し、自宅で民泊を始める際のローン控除の要件や影響を確認することをおすすめします。
自宅で民泊を始めるためによくある質問

自宅で民泊を始める際に、よくある質問をまとめました。
費用や手続き、収益性について詳しく解説します。
自宅で民泊を始めるための初期費用は?
初期費用は物件の状態や設備によって異なりますが、およそ10万〜50万円程度が目安といわれています。
既に居住している家を活用する場合、主な費用は清掃費、家具やアメニティの準備、消防設備の設置などが必要です。
ただし、新しく物件を購入する場合は、物件価格やローン費用も考慮する必要があります。
airbnbに登録するだけで自宅の一室を民泊にできる?
Airbnbに登録するだけでは、たとえ自宅の一室であってもすぐに民泊を始めることはできません。
民泊の部屋数に限らず、住宅宿泊事業法に基づく届出や、消防法令適合通知書の取得が必要です。
また、賃貸物件では管理会社やオーナーの許可、マンションでは管理規約の確認および管理組合の許可も必須です。
適切な手続きを済ませた上で、Airbnbやほかの予約サイトに登録し、運営を開始してください。
民泊は田舎の方が儲かりますか?
都心から離れた観光地や温泉地は、競争が少ない傾向があるため収益を得やすいといえます。
近年は、外国人観光客やワーケーション需要の高まりにより、田舎の静かな環境を求める宿泊者が増加傾向です。
ただし、都市部から離れるほど集客が難しくなります。
予約サイトを活用し、「地元ならではの体験」や「自然を活かしたアクティビティ」など、地域の魅力を前面に出す工夫をしながら、ほかの宿との差別化が必要です。
また、長期滞在プランや食事付きプランを提供することで、リピーターを増やす戦略も有効といえます。
茨城・千葉で民泊をお考えの方はクレアカーサへ相談を

民泊を自宅で始める場合は、リノベーションやリフォームが必要です。
宿泊者にくつろいでもらえる間取りや設備を取り入れ、利益に繋げるには信頼と実績のある工務店選びがカギといえます。
茨城や千葉で理想的な民泊を検討されている方は、クレアカーサにご相談ください。
豊富な知識と経験で、理想の民泊を提案します。
クレアカーサが、「ウチ+ソト+ニワ」のトータルデザインをコンセプトに、理想のマイホームづくりをお手伝いいたします。
オンライン無料相談やショールームでは、家づくりのプロが土地選びや資金計画、間取りの疑問・その他住まいに関するお悩みをうかがいますので、ぜひお気軽にご利用ください。