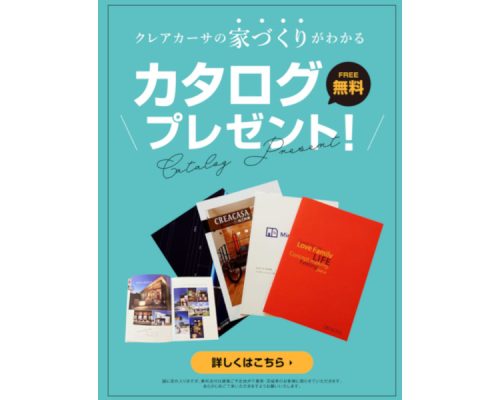別荘を民泊として活用するメリット・デメリット|民泊新法や民泊禁止エリアについても解説

都心に住む人がセカンドハウスとして物件を取得し、1年の半分を地方で暮らして残りの半分を民泊物件として収益化するスタイルが注目されています。
こちらの記事では別荘を民泊として活用する際のメリット・デメリットを詳しく解説します。
民泊としても活用しやすい別荘の施工事例などもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
コラムのポイント
● 民泊運用することで別荘を有効活用でき、維持管理コストを賄えたり、建物の劣化を防ぐメリットがあります。
● 別荘の民泊事業は民泊新法に沿った届出・運営・管理を行うだけでなく、近隣住民への配慮も大切です。
● 別荘としても利用しやすく、民泊の需要が高いエリアを選ぶことが重要なため、信頼できる住宅会社に土地探しからサポートしてもらいましょう。
別荘でも民泊事業はできる

個人が所有する別荘でも民泊事業を行うことは可能です。
ただし、民泊新法や自治体などが定めた様々なルールをクリアすることで民泊を始めることができます。
民泊新法と旅館業法の違い
民泊サービスを始めるには宿泊施設の営業を規定する法律や条例である「民泊新法」や「旅館業法」のどちらかに基づいた届出をしなければなりません。
民泊新法と旅館業法の主な違いをご紹介します。
| 民泊新法 | 旅館業法 | |
| 営業日数 | 年間180日以内 | 日数制限なし |
| 用途地域の制限 | 工業専用地域以外の用途地域 | 第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域 |
| 建築基準法上の建物用途 | 住宅や共同住宅など | ホテルまたは旅館 |
| 申請方法 | 都道府県への届出申請 | 都道府県への許可申請 |
民泊新法では住居専用地域でも開業できるため、別荘を建てるエリアの選択肢が広がります。
民泊新法は届出のみで申請が完了しますし、旅館業法と比べて申請書類が少なくて手間もかかりにくいです。
対して、旅館業法では営業日数の制限がない点が最大のメリットと言えます。
どちらの申請で民泊運用をすべきかを初めに検討することが大切です。
別荘とセカンドハウスの違い
別荘とセカンドハウスには次のような違いがあります。
| 別荘 | セカンドハウス | |
| 目的 | 保養を目的とした住まい | 日常的に寝泊りする住まい |
| 利用回数 | 利用頻度は決まっていない | 月1回以上利用する |
他にも、セカンドハウスは取得した際に固定資産税や不動産取得税の優遇制度を受けられるのに対して、別荘は該当しないなどの違いがあります。
今回は別荘についてお伝えしますが、セカンドハウスについても同様に民泊事業を行うことが可能です。
別荘を民泊運用するメリット

別荘を民泊として運用するメリットをご紹介します。
ご自身が宿泊しない期間も有効活用できる
別荘を民泊として運用すれば、ご自身が宿泊しない期間も有効活用できます。
お仕事やご家族の都合などで別荘を所有していても年に数回しか利用できていない方は少なくありません。
そこで民泊として貸し出すことで空き時間を価値に変え、賢く運用することができます。
維持管理コストを賄える
別荘を所有すると、次のような維持管理コストがかかります。
- ・税金:固定資産税、都市計画税、住民税
- ・維持費:電気ガス水道などの光熱費、通信費、火災保険料
- ・管理費:メンテナンス費、点検費用、管理依頼費用
ご自身の利用回数が少なかったとしても、毎月一定額のメンテナンス費は必要です。
民泊事業で収入を得ることができれば、上記の維持管理コストを賄うことが可能です。
稼働率が高まれば必要なコストを賄うだけでなく、収益化も実現します。
建物が劣化しにくくなる
民泊運用して別荘の使用頻度を上げることで建物が劣化しにくくなる点もメリットです。
人の出入りがない建物は換気が不十分になり、湿気やホコリなどが溜まりやすくなります。
湿気が溜まると内装材にカビが生えやすくなり、構造体の劣化にもつながりやすいです。
民泊運用することで人の出入りが増えますし、管理の回数も増えるため建物の健康を保ちやすくなります。

別荘を民泊運用するデメリット

別荘を民泊として運用するデメリットも確認しましょう。
民泊を始めるためには様々な手続きや準備が必要
民泊はただ集客をして泊まってもらうだけではなく、事業を開始する前に様々な手続きや準備が必要です。
具体的には次のような順序を踏まなければなりません。
- ①役所や消防署へ事前に相談(消防設備やエリア等)
- ②必要書類へ記入して管轄の行政機関へ届出
- ③行政機関が届出内容を審査・結果を通知
- ④届出が受理されたら内装工事や家具の設置など準備作業をする
- ⑤利用方法などの資料、細かな備品などを用意する
- ⑥民泊施設検索サイト(ポータルサイト)への住宅登録をする
運営開始までに時間と手間がかかるため、ゆとりを持ったスケジュールで進めましょう。
詳しくはこちらのコラムで解説しておりますので、チェックしてみてくださいね。
▶︎おすすめコラム:【自宅・別荘で民泊運営】個人での始め方やデメリット・注意点、失敗しないためのポイント
エリアや立地によっては管理が難しい
別荘が建っているエリアや立地によっては管理が難しい点がデメリットです。
ご自宅から遠い場合は頻繁に通うのが負担になるため、管理会社に依頼するケースも多いです。
しかし、別荘地などでないと対応してくれる管理会社が見つからない可能性もあります。
民泊事業を始める前に管理をご自身で対応するか、業者にお願いするのかを検討しておきましょう。
管理会社に頼む場合は事前に依頼先を見つけておくと安心です。
年間の営業日数を180日以内に抑えなければならない
冒頭でもお伝えした通り、民泊運用は「旅館業法」ではなく「民泊新法(住宅宿泊事業法)」が適用になります。
民泊新法では年間の営業日数を180日以内に抑えることが定められているため、一定以上の収益を得るのは難しい点がデメリットです。
「住宅宿泊事業」とは旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が180日を超えないものとされています。
本格的に民泊運用したいなら、旅館業法における簡易宿所営業も検討しましょう。
簡易宿所として旅館業法の許認可を取るのは民泊の届出と比べて難易度が高いですが、営業日数の制限がないため利益化が見込みやすいです。
どのくらい収益を得たいのか、ご自身で別荘を使いたい日数などを考えて申請方法を決めてくださいね。
近隣トラブルのリスクがある
一棟丸々借りられる別荘の民泊は大人数で宿泊しやすく、夜遅くまで楽しむ方も少なくありません。
また民泊は外国人の利用客が多い傾向にあるため、文化の違いによる騒音などのトラブルが発生する可能性もあります。
特に成田空港がある千葉エリアなどは海外旅行客も利用しやすいです。
長期的に民泊運用を続けるために、日常生活を送る近隣住民や別荘地で休息する方の迷惑にならないように対策しましょう。
民泊事業を始める前に事前に近隣住民へ説明して連絡先などを伝えておくことで、大きなトラブルを防ぎやすくなります。
宿泊者にも状況を伝えて配慮してもらったり、目の付きやすい箇所に多言語で注意書きしたりするなどの対応がおすすめです。
民泊運営とご自身の利用頻度のバランスが難しい
別荘を民泊として利用する場合、民泊運営とご自身の利用頻度のバランスに悩まれる方は多いです。
民泊として1番集客を期待できるのは年末年始やお盆、ゴールデンウイークなどの長期休暇ですよね。
またスキー場の近くなら冬季、避暑地なら夏季にニーズが高まります。
需要が高い時期に民宿をフル稼働させれば収益が上がりやすいですが、ご自身が宿泊したいときに利用できなくなる点はデメリットです。
収益を見込める営業日数を考え、ご自身の利用頻度を決めることが大切です。
1年中快適に過ごせるようなエリアを別荘地に選ぶことで、ご自身が利用するタイミングを調整しやすくなります。
民泊運営が禁止されているエリアがある
民泊が運営できるエリアが限られる点にも注意が必要です。
民泊新法では工業専用地域以外の用途地域で民泊運営が可能ですが、厳密には自治体のルールによって異なります。
別荘地では管理会社によって民泊運営が禁止されているケースも少なくないため、購入・建築前には必ず確認しましょう。
▶︎お電話でのお問い合わせ 0120-35-3436
民泊運営する別荘は建築エリアが重要

民泊運営する別荘は次のような理由から建築エリア選びが重要です。
- ・エリアによっては民泊の許可が下りない可能性があるから
- ・近隣トラブルにつながる可能性があるから
- ・集客を見込みつつ、ご自身の満足度の高いエリアを選ぶべきだから
別荘を購入・建築してから後悔しないように、エリア選びのポイントをご紹介します。
民泊禁止でないエリアを建築地に選ぶ
まずは民泊禁止でないエリアを建築地に選びましょう。
用途地域は問題なくても、市町村条例や別荘地の管理規約などによって民泊が禁止されていることも珍しくありません。
例えば千葉県では県として民泊営業を制限している地域はありませんが、市町村によっては地区計画や建築協定により営業できないケースがあります。
(参考:民泊について(住宅宿泊事業法)|千葉県)
規約を見たり直接問い合わせて、民泊運営が可能なのかを最初に確認しましょう。
音問題などを考慮して周辺環境をチェック
音問題などを考慮したエリア選びをすることで近隣トラブルを防ぎやすくなります。
例えば、隣家との距離が近すぎない立地なら音が気になりにくいです。
また、すでに民泊を運営している別荘が近くにあるなら近隣住民の理解がある可能性もあります。
現地を見に行く際には周辺環境や住んでいる方の雰囲気なども確認しましょう。
近隣住民と話せると、よりリアルな生活環境を把握できるためおすすめです。
別荘として活用しやすく集客を見込める立地を選ぶ
別荘として活用しやすく、民泊の需要も高い立地を選ぶことが大切です。
民泊として人気でもご自身が落ち着かない別荘では満足度は下がりますし、集客が見込めないエリアでは収益が上がりません。
海・山などの自然に囲まれていて静かに過ごすことができ、アクティビティも楽しめるようなエリアは人気が高いです。
都会へ出やすく自然のアクティビティも楽しめる「千葉県」は民泊の需要が高いエリアです。
民泊施設の検索サイトでは千葉県の「いすみ市・成田・銚子・木更津・八千代・船橋・館山・市川市・舞浜」が注目されています。
利便性も高いため、ご自身・宿泊者ともに利用しやすい民泊にしやすいです。
▶︎クレアカーサの提案する「二拠点生活+民泊に適したセカンドハウス」についてはこちらから
土地探しからサポートしてくれる住宅会社に相談を
別荘の建築地探しに悩む方は多いですが、民泊も可能という条件を追加するとさらに難易度は高まります。
そのため、土地探しからサポートしてくれるような住宅会社への相談がおすすめです。
民泊運営できる別荘の建築を前提として土地探しをしてもらえるため、ご自身の負担を軽減できます。
土地探しを依頼する際は民泊用物件の建築実績が豊富な住宅会社に相談しましょう。
クレアカーサでは施工範囲を千葉県内に限定し、高断熱・高耐震かつ省エネでスタイリッシュな住宅を提供しております。
別荘として活用しやすく民泊運営も可能な「土地探し」もお任せください。

▶︎お電話でのお問い合わせ 0120-35-3436
▶︎ショールームや各種イベントのご予約・お問い合わせはこちら
別荘の施工事例をご紹介
クレアカーサの別荘の施工事例をご紹介します。
①プライベートな中庭がある家

南側に面した壁には大きな窓を付けず、外部からの目線や強い日差しを気にせず過ごせるように。
家の中心部にはウッドデッキで中庭を設けプライベート空間を確保。
外部への開口は控えめにしながら内側へと広がるコの字型設計の平屋です。

勾配天井のリビングは開放感に満ち、こだわりの音響システムで映画や音楽をゆったり味わえるくつろぎ空間になりました。

ワークスペースはリビングと寝室に1つずつ設けました。
多彩な生活シーンを想定しプランニングされたセカンドハウスです。
▶施工事例:サーフ×リゾート 心身を解きほぐすセカンドハウス
▶おすすめコラム:
平屋の別荘で叶える二拠点生活|おしゃれな間取り・設備・デザインまとめ
ワンちゃんも大満足なドッグランがある家

白やライトグレーを基調とした、非日常感のある爽やかな雰囲気の住まいです。
LDKからはテラスとドッグランにつながります。

ワンちゃんが思いっきり走り回れる、大満足の空間です。
庭の一部にはバーベキューエリアも完備しています。

耐火性のある天然石の乱張りで仕上げられたスペースに、照明や日除けになるタープを付け、昼夜問わずバーベキューを楽しめる空間に仕上げました。
ペット可の民泊は需要がありますが、管理や設備の用意などに手間や費用がかかりやすいため、慎重に検討しましょう。
サウナやプールが楽しめるプライベートヴィラ

建物前にプライベートプールがあるリゾートスタイルのヴィラです。
自然に囲まれた広大な敷地で、人目を気にせずに過ごすことができます。
大人数で宿泊してもゆったりとくつろげる、広々とした一直線LDKです。

天井の高さに変化をつけ、梁を見せることで開放感あふれる空間に仕上がりました。
敷地内には、薪ストーブを使ったフィンランド製バレルサウナも完備しています。

特別感のある設備を採用することで、建物に付加価値をつけることが可能です。
クレアカーサは「敷地・家族・予算」の条件をお客様から細かくヒアリングし、トータル的にご要望を叶えられるプランを提案いたします。
高い耐震性・断熱性・省エネ性にこだわった家づくりに努めておりますので「コストもデザインも品質も諦めたくない」という方は、ぜひクレアカーサまでお問い合わせください。
まとめ

別荘を建築・購入して民泊運用することはできます。
ただし、エリアによっては民泊事業ができなかったり近隣トラブルにつながったりするリスクがあるため、事前にデメリットを知っておくことが大切です。
民泊運用を成功させるためにはエリア選びや需要に合った建物を採用することがポイントのため、別荘の施工実績が豊富な住宅会社に土地選びからサポートしてもらってくださいね。
私たちクレアカーサ(株式会社日立プロパティアンドサービス)は、千葉県茂原市にある建築会社です。
平屋建て・2階建てとレパートリー豊富な注文住宅や規格住宅の設計施工実績が豊富で、「高断熱+高性能設備+太陽光発電」のZEH(ゼロエネルギー住宅)の普及にも努めております。
「別荘・民泊でも快適で暮らしやすい性能を確保したい」という方をしっかりサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

家づくりのアイデアや施工事例をアップしています。ぜひフォローください♪